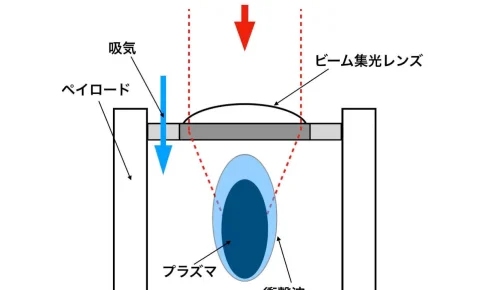KIT航空宇宙ニュース2024WK51
海外のニュース
1. JAL出資の米ブーム、超音速実証機XB-1がマッハ0.87記録 飛行試験9回目
超音速旅客機「オーバーチュア(Overture)」を開発中の米ブーム・スーパーソニック(Boom Supersonic、本社デンバー)は、技術実証機「XB-1」の9回目となる飛行試験で、過去最高のマッハ0.87(約1037キロ)と高度2万7716フィート(約8448メートル)を記録し、55分強飛行した。9回目の飛行試験は、これまでと同じカリフォルニア州のモハベ(モハーヴェ)空港・宇宙港で現地時間12月13日に実施。今回の試験で、XB-1はボーイング787型機の最高速度マッハ0.9やエアバスA350型機のマッハ0.89に近い値を記録した。また、修理後に再設置されたFES(フラッター励振システム)は、正常に動作したという。XB-1は、超音速に達するまでに10回の亜音速飛行を予定している。実証機のXB-1は2人乗りで、主翼の形状はデルタ翼を採用し、エンジンは既存のGE製J85-15が3基。アフターバーナーを使ってマッハ2.2(時速換算2335キロ)の実現を目指す。ブームは、XB-1で超音速飛行の技術を検証し、同社初の超音速旅客機であるオーバーチュアの開発につなげる。オーバーチュアはエンジンが4基となり、アフターバーナーを使わずに現在の民間航空機の2倍となる速度を実現し、マイアミからロンドンまで5時間弱、ロサンゼルスからホノルルまで3時間で結ぶ。ブームには日本航空も出資しており、実際に量産するオーバーチュアは、ユナイテッド航空などが発注している。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:9回目の試験飛行でマッハ0.87を記録した超音速実証機XB-1】
2.スマートフライヤー、革新的なSF-1で電動トレーニング革命を目指す
ヨーロッパ最大のコウノトリの営巣地および狩猟地から目と鼻の先にある低層の工場ホールで、野心的なスイスのパイロットとエンジニアのグループの熟練の手によって、新しい電動飛行機が誕生しつつある。スマートフライヤー社のSF-1は、洗練された高翼、三輪式ギア、単発ピストン航空機であり、飛行訓練に革命を起こし、コストを下げるとともに、騒音公害と化石燃料の排出を削減することを目指している。一見すると、目立つのは、突出した細長い機首、滑らかで軽い繊維複合材の胴体、広いラップアラウンドウィンドウ、尾翼の前向きのプロペラです。SF-1 は、現在市場に出回っているほとんどの単発ピストン練習機とはまったく異なるが、単なるそのような製品ではありません。燃焼エンジンを置き換えるのではなく、電気モーター用に一から設計された初の電気飛行機です。SF-1 は、オールカーボン構造、未来的な内装、そして今日の先進的な航空機設計にぴったり合う直感的な航空電子機器を備えている。大容量バッテリーで駆動する純電気エンジンは、排出ガスゼロで120ノット(時速222キロ)で2.5時間の飛行が可能。離陸時の出力は160kWで、215馬力に相当。飛行中に発電機を駆動してバッテリーを充電する小型燃焼エンジンであるレンジエクステンダーを追加すると、航続距離は約432海里(800キロ)になる。最終的に飛行持続時間が 5 時間を超える燃料電池駆動型を計画している。チームは、飛行学校の潜在的な顧客に対して、CO2排出量を 25% 削減し、運用コストを 50% 削減することを約束している。プロペラが尾翼に取り付けられているが、電動モーターは従来の燃焼エンジンの約 5 分の 1 の軽さであるため、プロペラを後部に配置することが可能で、プロペラが前部にあると、加速された空気塊が自由に流れ、広い胴体断面によって妨げられることがない。【Flightglobal news】

【Smartflyer提供:革新的な尾部搭載型プロペラが搭載されている電動飛行機SF-1】
3. ZeroAviaが水素燃料電池パワートレインの開発遅れの可能性を示唆
英国と米国の開発会社が公開した最新の認証スケジュールによると、ゼロアビアのZA600水素燃料電池パワートレインは2027年より前には運航を開始しない可能性がある。【Flightglobal news 】

【Flightglobal提供:ZeroAviaの水素燃料電池航空機】
日本のニュース
1. ANA、ピーチを完全子会社化 独自性維持に注目
NAホールディングスは12月20日、傘下のLCC(低コスト航空会社)であるピーチ・アビエーションの株式を全株取得したと発表した。今後成長が 期待できるピーチを完全子会社化することで、インバウンド(訪日)需要のさらなる取り込みを図る。一方、好調なピーチの独自性が維持されるかが注目される。直近の持株比率は、ANAHDが93.0%、就航当時大株主だった香港の投資会社ファースト・イースタン・アビエーション・ホールディングスが7.0%。ファースト・イースタンは段階的に売却しており、今回の売却でピーチはANAHDの100%子会社になった。ピーチは2011年2月10日にA&F Aviationとして設立され、同年5月24日に現社名に変更。2012年3月1日に就航した。ANAHDは2017年にピーチを連結子会社化し、同じく傘下のLCC、バニラエアを2019年11月に統合した。2022年12月27日には、初の中距離国際線となる関西-バンコク(スワンナプーム)線を、シートピッチが既存機より広い最新機材エアバスA321LR(1クラス218席)で開設。今月4日には、関西-シンガポール線を開設し、東南アジアで訪日需要が見込まれる2都市への就航を果たした。ANAHDは「これまでピーチが築き上げてきた企業文化やブランドの強みを活かし、アジアを代表するLCCを目指すピーチをサポートするとともに、ピーチとANAグループ各社との連携、協業を更に深め、『エアライン事業領域の拡大』と『事業性の更なる向上』をはかりANAグループの企業価値向上を目指してまいります」とコメントしている。今後は2017年の連結子会社化時にANAHDの片野坂真哉社長(当時)が言及した、「ピーチの独自性」をどれだけ維持できるかが、これまでの好調を維持し、ANAグループとしてシナジーを最大化できるかに直結していくとみられ、ANAHD側の出方が注目される。【Aviation wire news】
2.1月の羽田事故、運輸安全委が年内に経過報告「事実情報は出来る限り入れる」
国の運輸安全委員会(JTSB)の武田展雄委員長は12月17日、羽田空港で今年1月2日に起きた海上保安庁機と日本航空機の衝突事故について、予定通り年内に経過報告(中間報告)を行う方針を示した。一方、事故原因などの分析には時間がかかるとして、事故調査報告書の公表時期については明言を避けた。武田委員長は、経過報告の内容について「事実情報は出来る限り入れる」として、コックピットボイスレコーダー(CVR、操縦室音声記録装置)や飛行記録装置(DFDR)などの記録についても、内容により経過報告に含まれる可能性を示唆した。調査報告書の取りまとめに1年以上かかる場合、経過報告を出すことになっている。年内の経過報告後、調査報告書の取りまとめには時間がかかるとして、武田委員長は公表時期を「いつと言うことが言いがたい」と現状を説明しつつ、「社会的関心が強い事故なので、なるべく早い機会に分析し、社会に伝えるべきものがあれば、途中の段階でも提言なり、意見(の公表)はありうる」との考えを述べた。事故は1月2日午後5時47分ごろ、海保機MA722(ボンバルディアDHC-8-Q300、登録記号JA722A)とJALのエアバスA350-900型機(札幌発羽田行きJL516便、JA13XJ)がC滑走路で衝突し炎上。海保機は乗員6人のうち機長を除く5人が亡くなった。JL516便は乗客367人(幼児8人含む)と乗員12人(パイロット3人、客室乗務員9人)の計379人が搭乗していたが、全員が3カ所の出口から緊急脱出した。今回の衝突事故は、A350が初めて全損・全焼した事故であるとともに、CFRP(炭素繊維複合材)で胴体が作られた機体としても初の全損全焼事故となった。このため、今後の航空機の安全性を考える上で重要な事故調査となっており、2月の会見で武田委員長は、「衝突後火災に至った過程を明らかにし、今後いかに乗客をお守りするかという観点から、全世界的にも要望されていると思っている」と述べ、CFRP製の機体で起きた事故の特徴や、事故防止策の提言につながる調査を進める考えを示している。【Aviation wire news】

【Aviation wire提供:羽田空港での海保機との衝突事故後のJAL350型機の残骸】
3. アストロスケールのデブリ除去衛星「ADRAS-J」、デブリから約15mの距離まで接近に成功
アストロスケールは12月11日、2024年2月より進めている商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J(Active Debris Removal by Astroscale-Japan)」のミッションにおいて、観測対象のデブリから約15mの距離まで接近に成功したことを発表した。運用を終了した衛星やロケットなどのデブリは、地上との通信もできず、現在の状況を把握することが難しい。そのため、そうしたデブリへの安全な接近および捕獲を実現するためにも、対象物であるデブリの劣化状況や回転の速さなど、軌道上での状態を把握する必要があり、今回のミッションでは、そうした実際のデブリの除去に向け、安全な接近手法を実証し、手を伸ばせば届く距離までデブリに接近し、その状態を調査することを目的としている。今回のミッションで対象としているデブリはGOSATを打ち上げた「H-IIAロケット15号機」の上段。全長約11m、直径約4m、重量約3トンの大型デブリで、今回の接近は、JAXAのミッション要求とは別にアストロスケールが独自に実施した事業者独自ミッションであり、捕獲運用直前までのRPO(ランデブー・近傍運用)を実証し、将来のミッションに備えることを目的としたものだという。具体的には、まずデブリの後方50mの距離から、デブリと同一の軌道上を直進し、その後、将来デブリの除去としてその捕獲や軌道離脱も行う次のミッションである「ADRAS-J2(Active Debris Removal by Astroscale-Japan2)」で捕獲箇所として想定している衛星分離部(PAF)の下方に回りこんで接近、最終的には、同ミッションで対象デブリの捕獲運用開始を想定している距離(CIP)にまで接近し、相対的な速度、距離、姿勢を合わせる想定で、実際の運用では、これまでの近傍接近の運用と同様に、搭載センサでデブリの3D形状を高精度で測定し、その動きをリアルタイムで観測。自律的なナビゲーションシステムでそのデータをリアルタイムで処理し、デブリの動きを予測しながら自身の軌道や姿勢を制御しながら段階的に距離を縮めることに挑戦。接近や姿勢制御がこれまで以上に繊細で困難な極近距離において、慎重かつ精密な運用により、予定通りデブリの後方50mからPAFの下方約15mに機体を位置付け、一定の時間、相対的な距離と姿勢を維持することに成功したという。また、その後はADRAS-Jがデブリとの相対姿勢制御の異常を検知し、自律的にアボートを実施しており、最終的にはADRAS-Jはデブリから待避し、安全な状態を保っているという。【マイナビニュース】

【アストロスケール提供:対象デブリに接近するADRAS-Jのイメージ】
4. カイロス2号機宇宙に到達も軌道には届かず、正念場の2機連続失敗
スペースワンは12月18日、カイロスロケット2号機を打ち上げたものの、飛行中に異常発生。約3分7秒で飛行を中断し、打ち上げは失敗した。カイロスの打ち上げ失敗は、初号機に続いて2回連続。固体ロケットは液体ロケットに比べてシステムがシンプルであるものの、改めて新型ロケット開発の難しさが浮き彫りになった形だ。カイロスロケット2号機は、高層風の影響で2回延期されたあと、この日の11時00分に打ち上げが行われた。機体は順調に飛行を続けているように見えたが、同社によると、打ち上げ後80秒過ぎに、ノズルの駆動制御に異常が発生したという。第1段は姿勢を維持できない状態になり、地上からはタンブリングしているように見えた。明らかに正常な飛行状態ではなかったものの、その後もシーケンスは進み、第1段分離が約141秒(計画では148秒)、第2段点火が約142秒、フェアリング分離が約168秒(計画では175秒)に行われた。しかし、ここで事前に設定した飛行範囲を超えそうになったため、約187秒に、機体側の自律飛行安全システムが飛行を中断した。なぜ第1段の飛行中に自律飛行安全が作動しなかったのか。これについては、この段階では飛行を中断したときに部品が予想した海域外に落下することを避けることを主要な目的としており、姿勢の異常は条件に入っていないとのこと。第1段の飛行中から経路はズレ始めていたが、第2段の飛行中に限界に達し、そこで中断したというわけだ。ただ、正常な飛行でなかったとはいえ、第1段の燃焼終了まで行けたことで、機体の最高到達高度は110.7kmを記録。ミッションである人工衛星の軌道投入は果たせなかったものの、宇宙空間に到達することはできた。この点については、初号機からの大きな前進と言える。【マイナビニュース】

【スパースワン提供:上昇を開始した直後のカイロスロケット2号機】